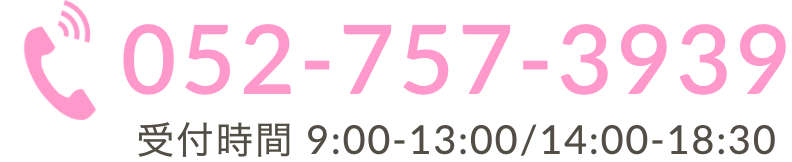
自律神経失調症の症状
自律神経失調症では、様々な身体症状があらわれます。また症状が出たり消えたりする場合もあります。
内科、耳鼻科、整形外科、婦人科、脳神経科、循環器科など複数の科を受診し、各種検査を受けるのですが、治療を要するような異常は認められません。そして原因不明のまま症状に悩まされることがあります。
一般的に自律神経失調症では、気分の落ち込み、不安、イライラといった精神症状はあまりみられません。
ただし、身体症状が改善しないことへの悩みが原因となり精神症状もあらわれることがあります。
【頭】
頭痛、頭重感
【耳】
耳鳴り、耳の閉塞感
【口】
口の乾き、口中の痛み、味覚異常
【目】
疲れ目、なみだ目、目が開かない、目の乾き
【のど】
のどの異物感、のどの圧迫感、のどのイガイガ感、のどがつまる
【手足】
手足のしびれ、手足の痛み、手足の冷え
【皮膚】
多汗、汗が出ない、冷や汗、皮膚の乾燥、皮膚のかゆみ
【循環器】
動悸、胸部圧迫感、めまい、立ちくらみ、のぼせ、冷え、血圧の変動
【呼吸器】
息苦しい、息がつまる、息ができない、酸欠感、息切れ
【消化器】
食道のつかえ、異物感、吐き気、腹部膨満感、下腹部の張り、腹鳴、胃の不快感、便秘、下痢、ガスがたまる
【泌尿器】
頻尿、尿が出にくい、残尿感
【生殖器】
インポテンツ、早漏、射精不能、生理不順、外陰部のかゆみ
【筋肉・関節】
肩こり、筋肉の痛み、関節のいたみ、関節のだるさ、力が入らない
【全身症状】
倦怠感、疲れやすい、微熱、ほてり、食欲不振
※自律神経失調症と関係の深い病気
症状が特定の部位に強くあらわれた場合には、別の病名がつけられることもあります。
以下のような病気は自律神経失調症の一種もしくは仲間ともいえます。
【神経系】
偏頭痛、緊張性頭痛
【耳鼻科】
めまい、メニエール病、乗り物酔い、咽喉頭異常感症
【口腔外科】
口内異常感症、舌痛症、顎関節症
【皮膚科】
円形脱毛症、発汗異常、慢性じんましん
【循環器】
心臓神経症、不整脈、起立失調症候群、起立性調節障害
【呼吸器】
過呼吸症候群、気管支ぜんそく
【消化器】
過敏性大腸症候群、胆道ジスキネジー、神経症嘔吐症、反復性臍疝痛、神経性下痢
【泌尿器系】
膀胱神経症、夜尿症、心因性排尿障害
【婦人科】
更年期障害
自律神経失調症の要因
以下のような様々な要因が複雑にからみあい、自律神経のバランスが乱れるといわれています。
- 体質的に自律神経が過敏、不安定である
- ストレスへの抵抗力、対処力が弱まっている
- 過度なストレスや過労が続いている
- 不規則な生活、睡眠不足が続いている
- 職場、学校、家庭の環境に大きな変化があった
- 思春期、産前産後、更年期、病中病後など、身体機能が変化したり弱まったりしている
自律神経失調症の治療
まずはご本人の悩み、状況、症状などについて、時には医師からの質問も交えながら、ご負担にならない範囲で把握させていただきます。診断のみを希望されて受診される方もおられますので病状についてご説明いたします。
自律神経失調症状は一時的なことが多く、十分な休養をとって生活リズムを取り戻せば、自然に軽快していきます。しかし、自分でうまくコントロールできない場合などは治療が必要になることもあります。
治療を希望される方には、治療の選択肢をご提案いたします。治療内容は、症状に合わせて薬を処方し、作用や副作用を確認しながら薬の調整を続けていく薬物療法が基本となります。抗不安薬や自律神経調整薬が主となります。症状や体質に応じて漢方薬を処方することもあります。
また、リラックス法である自律訓練法を習得すると自律神経が安定する作用があります。なお、うつ病など他の精神疾患に自律神経症状が合併している場合は、基礎となる精神疾患の治療が必要となります。
休職・休学中の方には、病状に応じて、週40時間の図書館学習やデイケア(リワーク・プログラム)通所などをお勧めすることもあります。
立ちくらみ
「立ちくらみ」は、本態性低血圧、症候性低血圧、起立性調節障害の3つに分けられます。
転倒し、外傷を負う危険性もありますので、注意が必要です。
本態性低血圧
原因となる病気が特にないのに、立っていても横になっていても常に血圧が低く、めまい、立ちくらみ、全身倦怠感などの症状があります。
症候性低血圧(二次性低血圧)
何らかの病気が原因で血圧が低くなる場合を症候性低血圧といいます。原因となる病気をつきとめ、その治療を行う必要があります。
症候性低血圧の中に食後性低血圧(食事性低血圧)があります。食事によって内臓の血管が拡張し、多くの血液が流入することで脳の血液が減るため、めまいや立ちくらみ等が現れます。高齢の方や高血圧症の方に多いといわれます。
甲状腺機能亢進症、鉄欠乏性貧血、心筋症、原発性肺高血圧症、副腎機能低下症、結核などの病気が原因となって、立ちくらみやめまいが起こる場合があるため鑑別診断が必要です。
起立性調節障害(起立不耐症)
横になったり座ったりしている時は正常血圧ですが、急に体を起こしたり、立ち上がったりした時にめまいや立ちくらみを起こします。高齢の方に多く、高血圧治療薬服用中にも起きる場合があります。
下半身に血液が流れ脳内の血液が少なくなるために生じることから「脳貧血」とも呼ばれます。しかし、もともと「貧血」とは血液中の赤血球数、血液中に占める赤血球の容積、および赤血球中のヘモグロビンが正常以下になる血液の病気をいいます。したがって、立ち上がった時に脳の血液が減って起こる「脳貧血」は「貧血」とは全く別のものです。
薬物治療として、メトリジン、ジヒデルゴッド、リズミックなどの薬を用いることがあります。ただし、甲状腺機能亢進症の方にはメトリジンは使えません。その他、症状や体質に応じて漢方薬を処方することもあります。
【日常生活で気をつけていただくこと】
- 立ち上がる時は、ゆっくり立ち上がる。
- 歩き始める時は、上を向かず、頭を前に曲げる。
- 規則正しい早寝早起きの生活を心がける。
- 朝食を摂取する。
- 昼間は横にならず活動するようにする。
- 長時間じっと立っていないようにする。
- 気温の高いところを避ける。
- 散歩などの運動を毎日15~30分程度は行う。
- 水分を1.5リットル以上飲む。
- 塩分を通常より3g程度多めに摂取する。
- 下半身に血液が留まることを予防するために、弾性ストッキングをはく。


