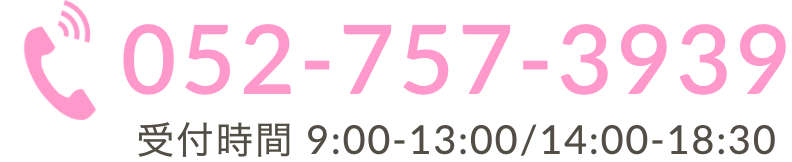
不眠症(睡眠障害)の症状
不眠症には大きくわけて3つのタイプがあります。またこれらのタイプが混合する場合もあります。
1.入眠障害
寝つきが悪い。寝つけさえすれば後はよく眠れ、目覚めも比較的良い。
2.中途覚醒
寝つくことができても睡眠の途中で何回も目が覚め、熟睡できない。
3.早朝覚醒
寝つきは良くても夜明け前から覚めてしまい、朝まで再入眠できない。
不眠症(睡眠障害)の要因
不眠症の要因としては、身体的なもの(疼痛、発熱、頻尿、下痢、いびき、等)、物理的なもの(環境変化、時差、交代制勤務等)、心理・精神的なもの(ストレス・失恋、失業、不安緊張、うつ病、アルコール依存等)、薬の副作用によるもの、等があげられています。
不眠について、長期化しているものは、不眠症としてしっかりと対処し精神科、心療内科等の専門医に相談することをおすすめいたします。長期化する不眠の原因としては心理的、精神医学的不眠が多く、睡眠薬のみでなく精神療法や精神安定剤を必要とするケースも多くあります。
睡眠薬はやめられなくなる、中毒になる恐ろしい薬だという根強い不安を持つ人がいます。しかし医師の指示通りに服用する限り、現在のベンゾジアゼピン系睡眠薬は依存症や副作用も少なく、安全で量の増える心配もありません。
<寝酒について>
飲酒による入眠は、入眠は円滑にしてくれますが、眠りが浅くなります。利尿作用により夜中に目が覚め、中途覚醒が増えます。反跳性不眠と言って一旦目が覚めると再度の入眠が困難となる事も度々です。量が増えると肝機能障害も引き起こします。飲酒量が増えている方は専門医への相談をお勧めいたします。
不眠症(睡眠障害)の治療
まずはご本人の悩み、状況、症状などについて、質問も交えながら、ご負担にならない範囲で把握させていただきます。症状に合わせて薬を処方し、作用や副作用を確認しながら薬の調整を続けていく薬物療法が基本となります。
なお、他の精神疾患に不眠症が合併している場合は、基礎となる精神疾患の治療も必要となります。
不眠症のほとんどは、超短時間作用型の睡眠薬を正しく服用すれば快適な睡眠が得られ、翌朝もすっきりと起きることができます。睡眠薬にも、強い物、弱い物もの、様々なタイプがあります。
また、作用の持続時間が長時間型のもの、中間型、短時間型、超短時間型等にわけられます。お一人お一人の不眠症の型、原因、程度に合わせて薬を処方いたします。症状や体質に応じて漢方薬を処方することもあります。
「睡眠薬は早く止めなくてはならない」と、急に服薬を止めてしまうと、かえって不眠症の程度が悪くなることもあります。専門医と相談しながら薬を徐々に減らして行くことが大切です。うまく調節できれば快適な睡眠と日常生活を得ることができます。


