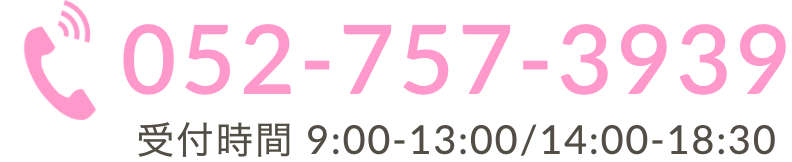
不安障害の症状
全般性不安障害は、特殊な状況に限定されない、理由の定まらない、原因がはっきりしない不安が持続的(半年以上)に続き、日常の出来事に対して過剰に不安になる、緊張が高まる、落ち着かない、疲れやすい、集中力が低下する、すぐイライラする、肩こりや頭重感、不眠などの症状があらわれます。そして日常生活に支障をきたすようになることもあります。
パニック障害の症状
パニック障害は、突然理由もなく不意に起こるパニック発作によって始まります。症状としては、激しい不安感、心臓がドキドキする、息がつまる、冷や汗、などの自律神経症状です。発作が起こると、「死んでしまうのではないか」という恐怖を感じるため、救急車で病院へ運ばれる例もしばしばあります。しかし、病院に到着した頃にはパニック発作のピークは過ぎ去り、先ほどの症状が、嘘のようにみられなくなります。病院で検査を受けても、何も異常はみられません。しかし、多くの場合、パニック発作は繰り返し起こります。そして、「また発作が起こるのではないか、大変な事態を招くのではないか」と心配し、発作を恐れるあまり日常生活が大きく制約されるようになります。
不安障害・パニック障害の要因
他の精神疾患と同様に、不安障害の要因としては、遺伝素因、生育環境、心理社会的ストレスなどが複合的に関与していると考えられています。
不安障害・パニック障害の治療
まずはご本人の悩み、状況、症状などについて質問も交えながら、ご負担にならない範囲で把握させていただきます。治療の必要性や見通しについてお話し、治療の選択肢をご提案いたします。
治療内容は、症状に合わせて薬を処方し、作用や副作用を確認しながら調整を続けていく薬物療法が基本となります。抗不安薬、抗うつ薬、β遮断剤などが主となります。症状や体質に応じて漢方薬を処方することもあります。
また、精神療法、認知行動療法も有用です。なお、他の精神疾患にパニック発作が合併している場合は、基礎となる精神疾患の治療が必要となります。
不安障害には抗うつ薬であるパキシルやジェイゾロフトが効果的な場合があります。また、抗うつ薬であるサインバルタが効果的な場合があります。
社会不安障害(対人恐怖症)の症状
社会不安障害は、10人に1~2人がかかるといわれるほどポピュラーな病気です。あがり症、赤面症、多汗症、視線恐怖症、体臭恐怖症、スピーチ恐怖症、書痙などがあります。社会生活に支障をきたしたり、人間関係の構築が十分にできなくなったりします。結果として引きこもりを伴うことが多くなります。
ご本人は「おかしな人と思われたくない」「弱みを見せたくない」「自分の性格が弱いせいだ」と思う傾向がみられます。しかし社会不安障害は、適切な治療を受けることで、比較的簡単に楽になることが多いといわれます。つらい症状が続き、仕事や家事などに支障が出たとき、また、不安や気分の落ち込みがあるときは、早めに医療機関を受診しましょう。
あがり症
他人の存在を過剰に意識する、他人の存在に緊張感や苦痛を感じる、職場や学校で自分だけが孤立したように感じる、他人とのつきあい方やコミュニケーションの方法がわからない、という症状がみられます。また、会議や披露宴などでスピーチをする際など特定の場面において、頭が真っ白になる、声が出ない、声が震える、などの症状がみられます。
赤面症
人前に立つと顔が赤くなる、人に注目される場面を過剰に意識する、人が集まる場所を避けてしまう、という症状がみられます。顔が赤くなっているのを指摘されることで人前が苦手になる場合もあります。
多汗症
人と接する時に緊張してぐっしょりと汗をかく、仕事の接客をしていると額からポタポタと流れるほどの汗をかくなどの症状がみられます。
社会不安障害(対人恐怖症)の治療
まずはご本人の悩み、状況、症状などについて質問も交えながら、ご負担にならない範囲で把握させていただきます。病気についてご説明し、治療の選択肢をご提案いたします。
不安感、恐怖などの心の症状や、震え、緊張といった身体の症状は、適切な薬を服用することによって、かなり改善されます。治療には主に3種類の薬を使います。
・SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
うつ病の薬として開発された抗うつ薬です。社会不安障害によく効き、緊張する場面でも不安を感じなくなる作用をもたらします。
・抗不安薬
緊張や不安をやわらげる作用があります。
・β遮断薬
震えや動悸、発汗などの身体症状を除去する薬を、人前で何かをする時のみ頓服として使うことで、状況に上手に対処できるようになり、自信を取り戻すことができます。
また、症状や体質に応じて漢方薬を処方することもあります。


